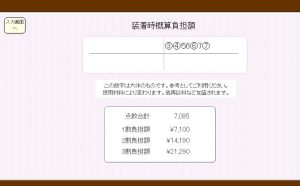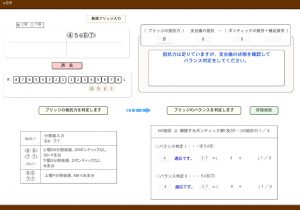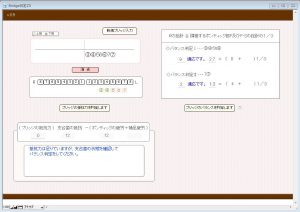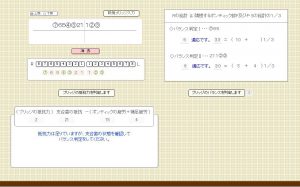愛用のカメラは、Pentax Kシリーズ
撮影素子は、APS-C
高解像度になると(1600万画素以上)こんな問題がありました。
以下「デジカメwatch ミニレポート 新ファームウェアで追加された「回折補正」を検証 」より
高画素化のために画素ピッチを詰めていくと、回折によって起きる「小絞りボケ」の影響を受けやすくなる。精細な描写を求めて高画素化した結果、細かいディテールを捉えることが難しくなってしまうわけだ。そのジレンマを解消するための研究を各カメラメーカーが進めており、K-3にもファームウェア1.10で「回折補正」機能として実装された。
2,400万画素・APS-C撮像素子のカメラで撮影する場合、回折の影響を無視できる限界は、計算上F8辺りで、さらに絞り込んでいくと解像力は徐々に低下する。高解像力/高解像度を保ちながら被写界深度を稼ぐには35mmフルサイズセンサーに移行するのが有利で、APS-Cに留まるなら、画素数を1,600万画素程度に抑えるしかないというのが従来の常識だった。それを覆す可能性を秘めているのが2,400万画素のAPS-C撮像素子と回折補正の組合わせだ。
回折補正機能は、レンズを絞り込むにつれて現れる解像力変化の状況を、各レンズ毎にデータベースとしてファームウェアの中に組み込み、それを逆引きすることで、失われかけていたディテールを演算によって復元する。光学的には克服できない限界を、コンピュータの力によってデータ上の問題として解決しようというアプローチだ。
同様の機能は、「点像復元」などの名前で他社でも採用が進んでいる。ベースになっているのはイメージプロセッサ「Milbeaut」第7世代に組み込まれた演算機能だといわれる
なるほど、これからの技術革新に期待をします。